過去の実習の様子(2019年度)BiologGing
2019年9月2日から5日までの4日間、函館市国際水産・海洋総合研究センター、および臼尻水産実験所にて、バイオロギング実習を行いました。2019年度は、全国から9大学17名、北海道大学から3名の学生が実習に参加しました。この実習では、ウミガメ類や魚類へバイオロギング機器を装着して海生生物の行動を追跡する手法を学び、水産生物の資源動態を把握する必要性について理解を深めました。
 |
海洋センターでの開講式の後、宮下先生のバイオロギングに関する講義から始まりました。バイオロギング研究の歴史や様々な機器の説明、具体的な研究例の紹介等、内容が盛りだくさんです。 |
 |
続いて、北海道大学水産学部の清水先生によるウミガメの講義を受けます。清水先生が実際に行っている、ウミガメを対象としたバイオロギング調査について、細かにレクチャーしていただきました。 |
 |
午前中の講義の最後は、白川先生による取り付け機器の説明と事前準備の方法についてでした。午後から実際に生物へロガーを取り付けるので、実習生たちは真剣に作業に取り掛かります。 |
 |
午後は生物の計測を行った後、ロガーの取り付け作業を行いました。今回取り付けたロガーは加速度と深度などを記録できる機器を使用しました。取り付け前には実習生にカメの曲甲長を計測してもらいました。ちなみに、こちらの写真は道南で混獲されたアカウミガメです。 |
 |
ロガーと水中カメラを取り付けたウミガメは、海洋センター内の大型水槽へ放流されました。これから2日間、水槽内での行動を記録し、得られるデータからどんな行動をしていたかを実習生に発表してもらうことになっています。 |
 |
実習生たちは1班1個体、好きな生物にロガーを取り付けました。今回の実習では、漁や釣りなどで事前に集めたイナダ、ボラ、アメマス、シマゾイを使用しました。生物の選択は、公平にじゃんけんで決めました。 |
 |
それぞれロガーの取り付け作業が終わると、無事に元気よく泳いでくれることを願いながら、大型水槽へ放流します。 |
 |
放流後のウミガメ。大型水槽へ入れた直後は水槽壁面によくぶつかっていましたが、しばらくすると落ち着いてのんびり泳いでいました。 |
 |
ロガーを取り付けられたアメマス。このアメマスを担当した班は、前にロガーを取り付けたサバではうまくいかず、3回目の挑戦でようやく成功しました。最後まであきらめないで、本当によく頑張っていました。 |
 |
本実習では、南茅部地区にある臼尻水産実験所に宿泊します。初日の夜は希望者のみ、臼尻水産実験所の近くにある温泉へ行きました。 |
 |
翌日はGPS機器をもって色々なところを歩き、自分たちの移動軌跡を取得、解析する方法を学びました。写真は国定公園の大沼公園です。晴天でGPSのデータ集めには最高の天気でした。 |
 |
移動軌跡は班ごとに取得します。各班、思い思いの方法で工夫を凝らしたデータを集めることに成功しました。この班は・・・スワンボートで沼を移動しているようです。 |
 |
この班は、途中にあったお店で一休憩をしているようです。GPSデータを解析すると、写真を見なくてもどんな行動をしていたか、すぐにバレてしまいますね!ということも身をもって体験しました。GPSを使った研究への応用についても解説してもらいました。 |
 |
大沼公園から次の目的地へ向かうまでの途中にある城岱牧場で記念写真。函館はあの夜景が有名ですが、実はここも函館裏夜景として知られるスポットなのです。お昼でもきれいな景色を一望できます。 |
 |
この日のお昼ご飯は、函館で有名なラッキーピエロ。フトッチョバーガーを注文して、小さな症状をもらいました! |
 |
お昼ご飯の後は七飯淡水実験所へ向かい、施設見学を行いました。この施設の屋内外ではサケマス類やチョウザメなどの魚類が非常にたくさん飼育されています。現在は行われていませんが、この施設でもバイオロギング実験が行われていました。 |
 |
今回の実習では、東洋大学の伊藤元裕先生にも参加していただき、海鳥におけるバイオロギング研究について講義をしていただきました。水中と陸上ではデータの取り方も異なるため、実習生たちは知識を吸収しようと真面目に講義を受けていました。 |
 |
3日目は、大型水槽に放流した生物を捕獲し、ロガーを回収することから始まりました。ウミガメと表層を泳いでいたアメマスは早々に回収されましたが、逃げ足の速いイナダとボラには苦戦。シマゾイに至っては狭い隙間に入り込んでしまったため、夕方になってようやく回収されたのでした・・・。 |
 |
生物の回収後、ロガーからデータを抽出するまでの間には、本学水産学部の富安先生による講義が行われました。魚類の行動や生態解明研究に加え、無脊椎動物を対象とした研究も紹介していただきました。 |
 |
さらに、その後には、実習に参加した院生らによる研究紹介も行われました。最新の研究を知る機会を設けたことで、今後の卒業研究にバイオロギングを希望している実習生たちは大満足だったようです。 |
 |
回収したロガーから抽出したデータの解析に取り掛かります。短期間で取得した全てのデータ解析は大変なので、今回は深度データの解析のみを行いました。アカウミガメは全員で解析し、あとは各班が担当した生物1個体のデータを解析しました。班で協力してデータを解析し、翌日最終日のプレゼンの準備を始めます。 |
 |
夏といえばBBQ。最後の夜はみんなで仲良く炭を囲んでBBQをしました。そしてBBQといえば花火ですね!最初は皆初対面でも、3日も経てば学生同士、すっかり打ち解けて仲良くなっています。 |
 |
最終日、忘れ物がないか確認してから、臼尻水産実験所を後にして、海洋センターへ向かいます。臼尻水産実験所から海洋センターまで、車で1時間の距離を運転してくださる先生方、大変お疲れ様です。。 |
 |
生物の回収後、掃除のため海水を抜いた大型水槽。こんなにも大きいんですよ。ちなみに、生物の観察は写真右側の窓から行っています。 |
 |
最終日のお昼ご飯は函館の老舗すき焼き店「阿さ利」のすき焼き弁当。最終日には毎年決まってこのお弁当を注文するほど、教員側も楽しみにしているお弁当です。 |
 |
午後の発表前に、急遽、伊藤先生にジオロケーターの講義をしていただきました。水中では使うことができないものですが、実習生の中には陸上で研究している学生もいるので、解説の場を設けました。伊藤先生、ありがとうございました。 |
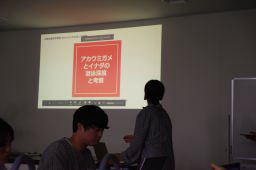 |
実習の最後に、班ごとに分かれて、大型水槽で集めた深度データをもとに研究発表をしてもらいました。皆、しっかりとデータをまとめて考察していて、短時間で完成度の高い発表をしていました。やる気のある学生が集まると、こんなにも質の高い発表になるのかと、感心しました。 |
 |
実習に参加した皆で集合写真を撮りました。4日間、本当にお疲れさまでした!ここで学んだことを、ぜひ、それぞれの研究に活かせることを願っています。 |
 |
発表も終わり、皆清々しい笑顔です。2020年も引き続き開催しますので、興味のある方はぜひご応募ください! |
-
実習生からの声
- 北海道のご当地グルメがおいしかったです。せっかく、有名ですごい先生方がいらっしゃったので、レポートの添削をしていただければと思いました。
- 豊富な知識を得られただけでなく、先輩方の研究内容や取り組み意欲なども知ることができ、本当に勉強になりました。
- インターネットではわからないバイオロギングに関する技術が学べて、とても充実していました。私は現在シロザケに関する研究を行っているので、今回の実習で得た知識と経験を活用したいと思っています。またこのような機会を用意していただける時には是非参加させていただきたいです。ありがとうございました。
- データから、何故この生き物がこのような行動をとったのか、分からないなりに想像して考察する面白さを体験できたのが、今後の自分の研究に活かせると思うので、一番の収穫でした。
- 深度データの可視化や魚類・カメといった生物でバイオロギングを学べたことは自分の研究や今後の調査に大きく役立てると思った。また、他大の学生と交流を深めることで、他大で展開されている研究も知ることができたので参加してよかった。
- バイオロギングはデータを取る方法に注目されがちだが、得たデータの解析と考察も重要であると感じた。他大学との交流を深めることができ、学ぶことが多く充実した実習だった。
- プログラムの内容のすべてよかったです。
- 最後の発表までの時間が短く感じました。加速度をやりたかったです。
- 大学の先輩が、他大の人ととても仲良くなれる実習だよとおっしゃっていたのですが、その通りでした。先生方も雑談してくださり、とても楽しかったです。TAの方々にも大変お世話になりました。
- バイオロギングは産業に役立つのか疑問に思い、本講義を受けました。バイオロギングは学術的価値が高いため研究が進められており、人の好奇心が学術に繋がることの重要さが学べました。
- 自分の研究対象と、魚と鳥と違いはありましたが、ロガーについては具体的なビジョンが生まれたので、参加してとても有意義だったと思いました。また、他大学の色々な知識を持った人と交流するのも、刺激的で良かったです。
- 大変有意義な時間でした。今後の進路に間違いなく影響すると思います。
- 実際にカメや魚に触れての実習をすることができて非常に有意義だった。バイオロギングの機材装着やデータ解析など自分の手で行えて、良い経験ができた。
- やりたかったバイオロギングをがっつりできて楽しかったです。観光の時間が思っていたよりも多くて驚きました。有意義な時間をありがとうございました。
- 現在研究者として活躍されている方々や、先輩方から多岐に渡ってお話をすることができて有意義であった。
copyright©2020 Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University all rights reserved.