6月12日(木)、酪農学園大学附属とわの森三愛高校にて、畜産を学ぶ高校生たちを対象に未来志向型ワークショップを開催しました。
このワークショップのテーマは、「2050年の畜産業とその社会を、自らの手で描いてみること」。
「きつい」「きたない」「儲からない」といったマイナスイメージを抱かれがちな畜産業に対し、未来を担うZ世代がどう向き合い、どのように変えていけるのか。
彼らの柔軟で斬新な発想と創造力を、コマドリアニメーションという手法を通して形にする試みでした。

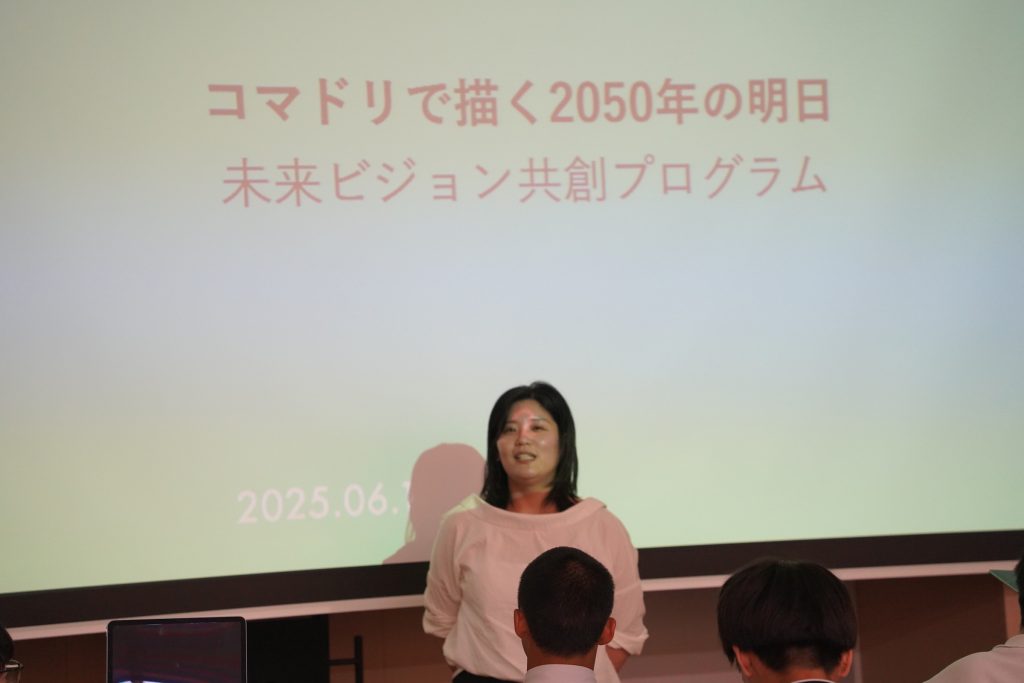
身近な畜産から見えた、「遠くの未来」
参加した高校生たちは、普段から畜産に近い環境にあるからこそ感じる現実の課題と、未来に期待する変化の狭間で、短時間ではありましたが、たくさんの「問い」と向き合いました。
「理想の牛舎」というワークテーマに対し、「すぐに“これだ”とは思い浮かばなかったけれど、自問自答することの大切さを知った」という感想には、探究の入り口に立つ若い世代の真摯な姿が映っていました。
また、「未来のことを考えるのはこれまでなかったけれど、楽しく考えられてよかった」という声や、「コマ撮りで動かしてみることで、未来を“実感”することができた」といった感想からは、単なる学習ではなく、想像と表現が融合する体験の価値が伝わってきました。



「食」の根本と「働く」ことの意味に向き合う
「食料の大切さがよく分かった」「今後の酪農について考える良い時間になった」「酪農の現状や技術がよくわかった」など、参加者の多くがワークショップを通じて、「食べること」「働くこと」「未来に生きること」について改めて考える時間を持てたようです。
そこには、単に職業としての酪農を考えるだけでなく、地球環境の変化や持続可能性といった、より大きな視点から畜産業の未来をとらえる姿勢も見えてきました。
また、本学の先生による講話をきっかけに、「話を聞けて、今後の生活の糧になった」と語る生徒もいました。



若い世代が未来を語る力
ワークショップの終盤には、各グループが制作したアニメーションを共有。そこには、環境や動物福祉、テクノロジー、地域社会とのつながりといった多様な視点が盛り込まれており、まさにZ世代だからこそ持てる想像力と問題意識が反映されていました。
未来を変えるのは、今を生きる一人ひとりの「問い」から始まります。
畜産を知り、感じ、動かしてみたこの一日が、生徒たちの中に小さな種となり、やがて大きな未来を育んでくれることを願っています。



