
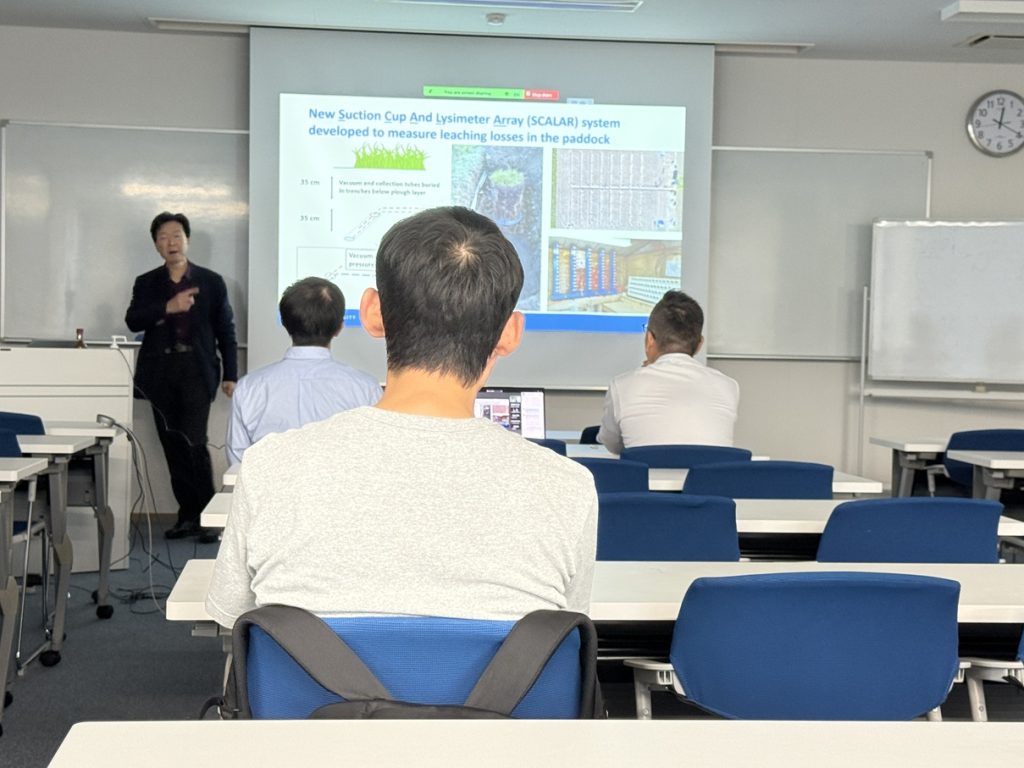
今回、ニュージーランド・リンカーン大学からHong Di教授をお招きして、セミナーを実施しました。Hong Di教授は、農業生態系における窒素循環、温室効果ガス排出、水質汚染の抑制技術に取り組み、土壌微生物の働きを通じた環境負荷の軽減を目指した研究を行っている先生です。今回は温室効果ガス排出の要因と測定方法、特に農業分野における窒素循環、微生物による土壌プロセス、農業実践が排出に与える影響に焦点を当てて解説していただきました。
私たちの暮らしを支える農業。その裏側では、目に見えない「窒素」の動きが、作物の成長だけでなく、地球環境にも大きな影響を及ぼしています。今回の議論では、農業における窒素循環の複雑さと、それがもたらす環境負荷の現実に焦点が当てられました。
窒素は、トウモロコシなどの作物の生育に不可欠な栄養素です。農場では、乳牛や豚の排せつ物を含む有機物や肥料によって窒素が供給されます。しかしその後、土壌中ではバクテリアの働きにより、窒素はさまざまな形に変化しながら循環します。この過程で発生するのが、メタンや一酸化二窒素といった温室効果ガス。私たちが普段意識することの少ないこのプロセスが、気候変動と深く関わっているのです。
研究では、特定の細菌による尿素の分解や、光の強さ・気温による影響も明らかにされました。シミュレーションによって「数百マイル分の窒素効率」や、「水と海での窒素の出会い」といった仮説も立てられ、新たな視点からのアプローチが模索されています。
さらに、排水設備の改善、大型の地中型貯蔵施設、環境に配慮した作付け計画など、技術と発想の力で、農業と環境の両立を目指す動きが加速しています。しかし、現在主流の方法(たとえばメタンや二酸化炭素の活用)は、まだ効率が十分とは言えません。
沈黙の温室効果—―畜産と見えない排出—―
こうした農業分野における温室効果ガス排出への理解を踏まえると、牛の放牧や畜産に起因する排出も、現在深刻な社会的課題の一つとなっています。特に、反すう動物によるメタンの発生、排せつ物からの一酸化二窒素の排出、さらには過剰施肥による硝酸塩の流出などが環境への影響として顕在化しています。放牧主体の畜産は、土地利用や土壌微生物活動と密接に関係しており、その実践が温室効果ガス排出の要因となり得ることが、近年の研究によって明らかになりつつあります。畜産のあり方を見直し、緩和技術の導入や栄養管理の工夫によって、持続可能な農業を追求していくことが求められています。
だからこそ、今、私たちは立ち止まって考え直す時に来ているのではないでしょうか。
自然の力を借りながら、未来の地球を守る農業をどうつくっていくのか。小さな微生物の営みからも、そのヒントは見えてきます。
「環境にやさしい農業」は、もはや理想ではなく、私たちの責任です。
一粒の種にも、一頭の命にも、未来が宿っています。 土を耕す手にも、家畜を育てるまなざしにも、地球との対話が存在します。 今こそ、農と畜の現場から、持続可能な未来に向けて環境と真剣に向き合う時です。



